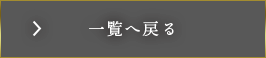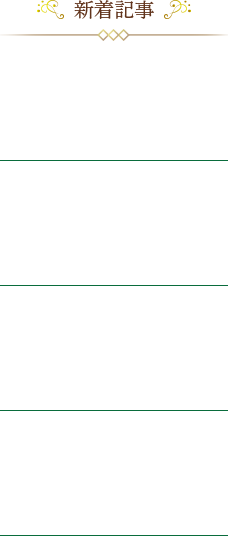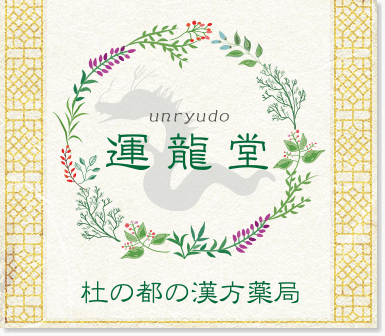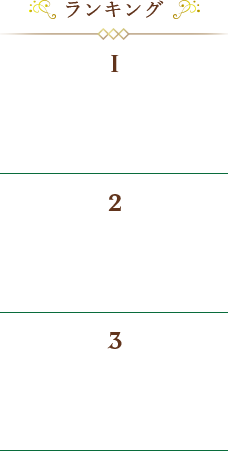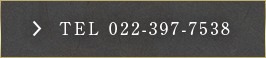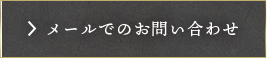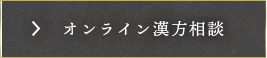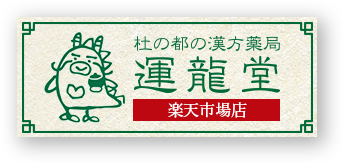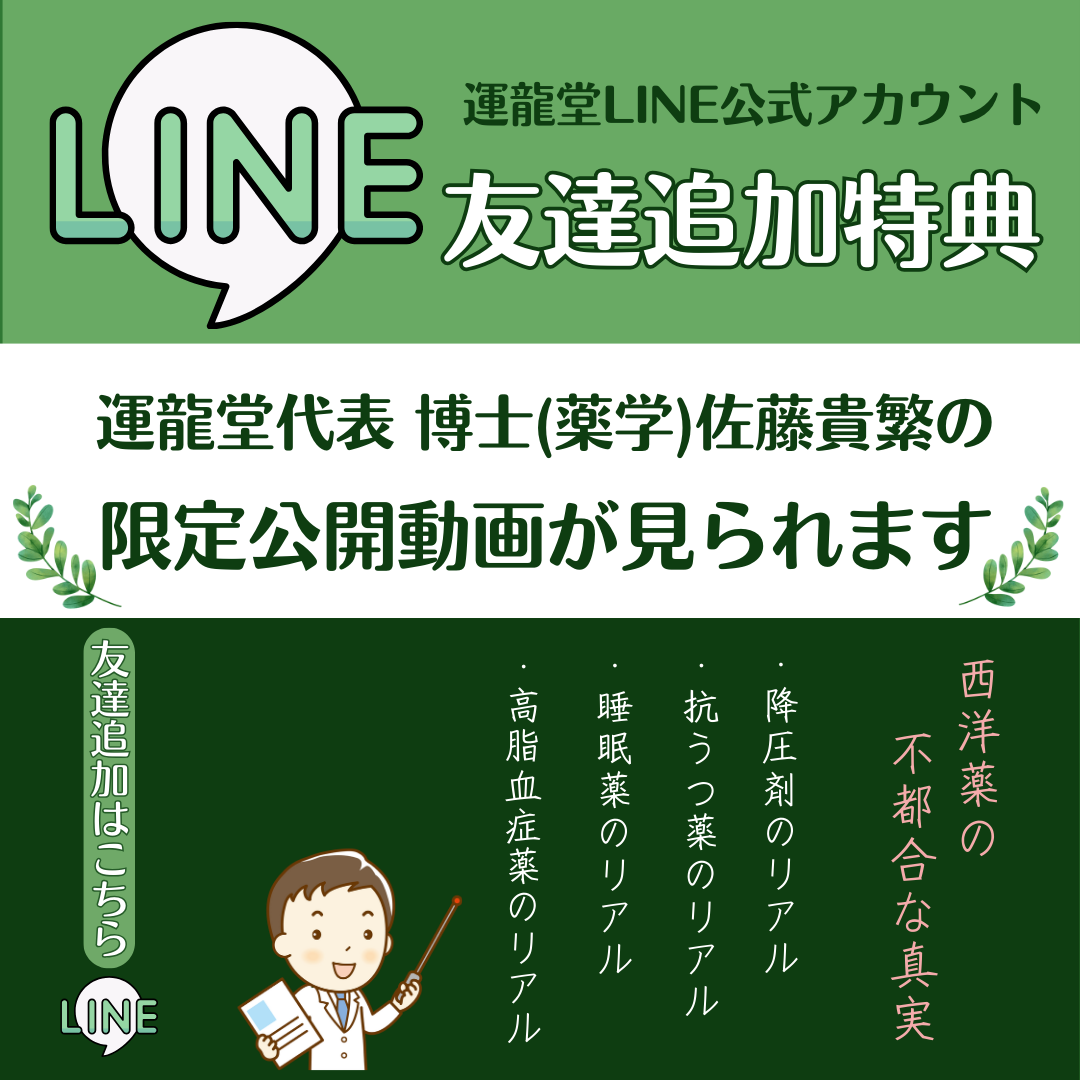がん対策の漢方

【アルブミンを維持し、炎症を抑える】
漢方でがん対策をするのは、効果が無いと思っている方も
多いのではと思います。
しかし、様々な臨床データががん対策に漢方が有効であることを
示しております。そして、その臨床データは年々増えております。
例えば、
・治療や予防を目的とする:免疫力の調整
・化学療法の副作用を軽減する
・放射線治療の副作用を軽減する
・外科的手術からの回復を早める
・緩和ケア(生活の質をあげる)
などにおいて、漢方の効果が認められております。
様々な対応が可能ですが、漢方で出来ることを集約すると
主に次の6つとなります。
①がんのアポトーシス:フコキサンチンが得意
②慢性炎症の抑制・抗がん剤の副作用軽減
③血管新生の抑制:フコキサンチンが得意
④免疫調整(腸管免疫も含む):スピルリナ、植物発酵ドリンク
⑤栄養管理(食養生): CoQ10でTCA回路を回す。
⑥抗ストレス(自律神経の調整)
この6つの対策の目的は、
副作用やストレスの軽減、そしてアルブミンの値を高く保ち、
C R Pを低くすることです。
副作用は様々ですが、意外と見落とすのが循環器系です。
アントラサイクリン系:心不全、
不整脈アルキル化剤:心不全、不整脈
HEP2阻害剤:心不全
微小管阻害:不整脈
免疫チェックポイント阻害剤:血栓塞栓
このように抗がん剤の副作用としては、循環器系も多いのです。
そして、もう一つの大きなポイントは、
「アルブミンの値を高く保ち、C R Pを低くする」ことです。
アルブミンは、肝臓において作られるたんぱく質で様々なものと結合し、細胞へ届けます。
もしアルブミンが70%へ低下すると窒素死が引き起こされてしまいます。
また、アルブミンの低下で低体温かつ浮腫みやすくなってしまいます。
またCRPは、炎症のマーカーです。CRPが増えている時は、アルブミンが減りやすくなってしまいます。
したがって、「アルブミンの値を高く保ち、C R Pを低くする」ことは、非常に重要です。
【漢方で出来る6つのこと】
【アルブミンを維持し、炎症を抑える】でお伝えした通り、がん対策で重要なのは、副作用やストレスの軽減、そしてアルブミンの値を高く保ち、
C R Pを低くすることです。
漢方で出来ることを集約すると
主に次の6つとなります。
①がんのアポトーシス
②慢性炎症の抑制・抗がん剤の副作用軽減
③血管新生の抑制:フコキサンチンが得意
④免疫調整(腸管免疫も含む)
⑤栄養管理(食養生): CoQ10でTCA回路を回す。
⑥抗ストレス(自律神経の調整)
上記を理解する上で、最初に理解しなくてはいけないのは、
がん細胞の特徴である「血管新生」と「エネルギーの作り方」です。

【血管新生について】
がん細胞は、血管を新たに生み出すための血管内皮細胞増殖因子(VEGF)を分泌します。その結果、血管の細胞は急激に増加します。これが血管新生です。
すると新しい血管と繋がり、栄養の供給量を増やし、
腫瘍は一気に大きくなってしまいます。
さらに、がん細胞は、血管に入り込み、他の場所へと移動できるようになります。
これが転移です。
したがって、血管新生を抑えるのが重要となるのです。
【細胞のエネルギーの作り方】
次にエネルギーの作り方です。
まずは一般的な細胞のお話をします。

細胞は、ブドウ糖からATPというエネルギーを作り出しています。
最初は、酸素を使わないで、一つのブドウ糖から2個のATPを作っていました。
この過程を解糖系と呼び、ミトコンドリアの外で作られています。
その後、進化の過程で酸素を使い、さらに36個のATPを作れるようになったのです。
この過程をクエン酸回路と電子伝達系と呼びます。
こちらはミトコンドリアで行われます。
難しい過程は抜きに、ミトコンドリアのおかげで、酸素を使って、たくさんのエネルギーを作れるようになったのです。
ところが、がん細胞はちょっと違うのです。
【がん細胞のエネルギーの作り方】
がん細胞は、何と酸素を使わない、解糖系がメインになっているのです。
反応が単純なので、スピードは早いのですが、大量の栄養を使いながら、
エネルギーを作り出しています。
考えられる理由としては、、、
(1)解糖系は、反応の段階が少なく、エネルギーを早く作れる。
(2)酸素を使わないため、がん細胞にダメージを与える活性酸素が生まれない。
(3)解糖系の過程で、がん細胞の分裂に必要な核酸が生まれる。
などが挙げられますが、対策としては、
酸素を使ってエネルギーを生み出すミトコンドリアの働きを上げることが重要です。
ここで少しまとめますと、
がん細胞の特徴である
「血管新生」は、他から栄養をたくさんとって、がん細胞の増殖と転移の原因となるので、
血管新生を抑えることが重要です。
またがん細胞は、ミトコンドリアを使わない非効率な「エネルギーの作り方」をしているので、
ミトコンドリアの働きを促すことが必要です。
それでは、6つの対策の話に戻りたいと思います。
①がんのアポトーシスについては、菌糸体が得意です。
また①がんのアポトーシスと③血管新生の抑制については、
「フコキサンチン」が得意です。
がんのアポトーシスとは、がん細胞に自分から死ぬこと。
血管新生については、これまでに説明した通りです。
【菌糸体について】
有名な菌糸体としては、以下のものがあります。
・アガリクス
抗腫瘍効果(特に腹水ガンやS状結腸ガン、肺ガン、 肝臓ガン、卵巣ガン、乳ガンに有効 )
・霊芝
抗腫瘍効果、抗アレルギー&抗ヒスタミン作用、血圧安定作用、 血糖値降下作用、血栓予防、高脂血症の改善、動脈硬化の予防、 胃酸過多、胃潰瘍、自律神経失調症、神経衰弱、慢性疲労の改善など
・メシマコブ
抗ガン・抗ウイルス活性作用。胃痛、下痢、血尿、脱肛、下血、 月経不順、リンパ腫、鼻血、渋り腹、排尿異常に効果。
・梅寄生茸(ばいきせいたけ):サルノコシカケの一つ
抗腫瘍効果(特に食道ガンに有効 )
※吸収されやい水溶性のβ‐グルカンが多い
・冬虫夏草
抗腫瘍効果、血圧調整作用、滋養強壮、心肺機能強化、胃潰瘍の予防、 喘息の予防、心因性ストレスの予防
この菌糸体は、色々な研究で有効性が認められておりますが、
ポイントが2つあります!
そのポイントは、「β‐グルカンの吸収効率」と「複数種類の服用」です。
※β‐グルカンの吸収効率
β‐グルカンは、様々な菌糸体に含まれ、免疫力低下に対してはそれを上昇させ、過剰の場合はそれを低下させる作用があります。したがって、免疫力が低下するガンの治療にも、免疫力が過剰となっているアレルギー症の抑制の両方が期待できます。 ただし、通常の服用では、 β‐グルカンの吸収率が非常に低いという問題が存在します。したがって、β‐グルカンの吸収効率の高い製品を選択する必要があります。
※複数種類の服用
β‐グルカンが多く含まれる菌糸体としては、例えば、アガリクス、霊芝、冬虫夏草などが有名ですが、1種類のみの服用だと、効果が持続しない場合が多いのです。したがって、複数の菌糸体を組み合わせて、服用することが必要となります。
【フコキサンチンについて】
フコキサンチン( Fucoxanthin )とは、コンブやワカメなどの褐藻類に含まれている、赤褐色の天然色素です。よく混同される成分に「フコイダン」は全く別物です。
フコキサンチンは【色素】:抽出効率0.003~0.01%
フコイダンは【多糖体】 :抽出効率0.2~1%
<フコキサンチン>
海藻表面のぬるぬる物質の内側にある表皮から取れる色素成分(赤褐色)。カロテノイドの一種で、ガン細胞の増殖や転移を阻害してアポトーシスを誘導します。
<フコイダン>
多糖類であり、褐藻の表面を覆っているぬるぬる成分。分子量が大きく、吸収率があまり良くないです。腸管内の免疫細胞に働きかけ、免疫力を高めることが知られています。
違いを簡潔に言うと、
フコキサンチンはガン細胞に直接働きかけて抑制して、フコイダンは免疫の働きを活性化して間接的にガン細胞を抑制します。
※フコキサンチンの働き
・血管新生抑制する。
・抗がん治療による炎症性物質の増加を抑制する。
・気分障害、うつ発症を防ぐ。
※炎症性物質の増加により副腎からのホルモン分泌が乱れ、気分障害、うつを引き起こします。
・レチノイン酸作用=がん幹細胞の自己複製能を抑える。
※フコキサンチンは、レチノイン酸作用を持つ唯一のカロテノイドです。
※レチノール(がん促進)を、レチノイン酸(=がん抑制)へ変換する酵素は、がん幹細胞において、欠損しています。
※レチノイン酸は、アレルギーや喘息を改善します。
・その他、肥満、糖尿病、アルツハイマーなどにも応用。
④免疫調整(腸管免疫も含む)
こちらに関しては、植物発酵ドリンクを活用します。
腸内環境の改善は免疫の調整に深く関与します。

⑤栄養管理(食養生)
こちらについては、CoQ10でミトコンドリアの働きを活発にさせます。
美容で有名なCoQ10ですが、これはミトコンドリアの機能と関係があるのです。
⑥抗ストレス(自律神経の調整)については、下記の図がわかりやすいです。
がん患者にとって、精神的な疲労も大きな問題となります。
そこに炎症も関与します。
ストレスや炎症は、脳を介して、副腎からのホルモンバランスを変えます。
この状況が続くと、副腎は疲労し、脳血流が低下します。
(副腎疲労の詳細については、こちらを参照してください:https://unryudo.com/test/health-info/fukujinhirou/)
この結果、肉体的にも精神的にも疲弊してしまうのです。
最初のストレスや炎症に対応できるのが、先ほど紹介したフコキサンチンや
気の巡りを改善する麝香(ジャコウ)、そして牡蠣肉エキスなどです。
牡蠣については、脳内へ移行する抗酸化物質が最近見つかりました。
また副腎の対応として有名なのが
鹿の角である鹿茸となります。
ただし、鹿茸は性ホルモンのバランスを整える力もあるので、
性ホルモンを抑制するような治療が必要な時は注意が必要です。
また牡蠣肉エキスも副腎からのホルモンバランスを回復させる力があります。
以上のように、漢方でも様々ながん対策が可能となります。
この記事の監修薬剤師

運龍堂 佐藤貴繁
略歴
1977年 北海道生まれ。北海道立札幌南高等学校
北海道大学薬学部を卒業
2003年 薬剤師免許を取得
2006年 北海道大学大学院薬学研究科生体分子薬学
専攻博士後期課程を終了後、博士(薬学)取得
2011年 福祉社会法人 緑仙会理事 就任
2012年 杜の都の漢方薬局 運龍堂 開局
2013年 宮城県自然薬研究会会長 就任
2017年 宮城県伝統生薬研究会会長 就任